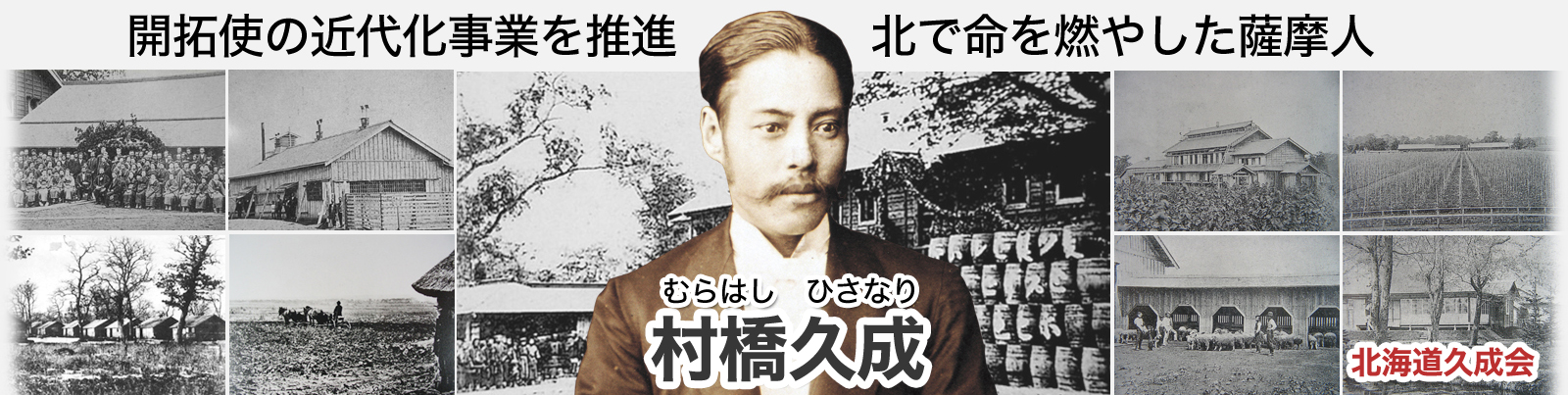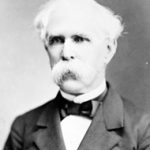
ホーレス・ケプロン
教師頭兼顧問。明治4年(1871)7月、アンチセル、ウォーフィールド、エルドリッジらを伴い来日。
黒田清隆の要請で現職のアメリ力合衆国農務局長から開拓使顧問へ転身。受諾の理由は、日米両国の「友好関係に貢献する」という使命感とともに経済的な事情もあったといわれる。
東京滞在で、4年間で北海道に来たのは3度だけだが、数次の報文を提出した。そこに挙げた指摘はその後の北海道にとって重要な指標・示唆となった。
黒田の信頼は勝ち得ていたが、お雇い外国人の仲間との間は、職務上も人間関係においても必ずしも好いとはいえなかった。特にアンチセルとの関係は険悪であった。またダンもケプロンについて回想録の中で「官僚的上役風」と書き残しているように批判的だった。

トーマス・アンチセル
明治4年(1871)7月、来日。地質・舎密(化学)・鉱山担当。
8月に来道し炭鉱の調査をしながら 函館から札幌に移動中、岩内地方のホリカップで ホップが自生しているのを発見。開拓使に 北海道でビールの醸造を始めることを建言した。
上司であるケプロンと考えが合わず、また頭越しに自身の待遇改善交渉を行い、ケプロンに更迭されるが、開拓使と交渉し明治5年(1872)仮学校の教頭になる。
明治7年(1874)に開拓使退職後、大蔵省紙幣寮に雇用され、紙幣の印刷に用いるインクの研究・精錬に従事して日本の紙幣製造に大きな功績を挙げる。

エドウィン・ダン
明治6年(1873)7月、牛とめん羊を引き連れて来日。父の牧場で牧畜業を習得。ケプロンの次男のすすめで、農業技術指導者として来日。東京第3官園の経営に就く。
七重、札幌では牧牛場、牧馬場、牧羊場などの設定準備、有料家畜の輸入、品種の改良、農耕・牧畜の指導に当り、真駒内では米国式の近代牧場経営を実践。北海道の農畜産を「産業」として発展させるため、試験・研究・指導を精力的におこなった。日本で初めて「去勢術」を指導。
七重でつると出会い結婚、日本永住を決めた。真駒内用水路の建設や町村金弥ら多くの優秀な農業経営者を育成するといった功績も大きい。
開拓使廃止後は、外交官となり在日公使として働き、公使辞任後は石油や造船事業を手がけ、東京代々木の自宅で永眠した。

ルイス・ベーマー
明治4年(1871)12月来日。東京官園第1、2で寒冷地に適する疏菜、果樹の品種を研究し、特にリンゴの増殖に成功。
明治9年(1876)5月、ダンと共に札幌官園に転勤し、麦酒醸造所のために北2条西3丁目から北5条にかけて5,500坪のボツプ園を造成した。
偕楽園や豊平館などの庭園設計を手がけるが、造園家であるだけでなく、全道各地を精力的に廻り植物相の調査や標本の採集を行い、植物学においても功績がある。

ベンジャミン・ルイス・ライマン
明治5年(1872)来日。アンチセルの後任としてケプロンが選んだ。地質学者、鉱業技師長として、北海道の地質測量に従事しながら、開拓使仮学校の生徒に実地教育をした。
日本最初の総合的地質図「日本蝦夷(えぞ)地質要略之図」(1876年)を作製。石狩炭田をはじめ、油田、金属鉱山の調査を行い、幌内炭田を発見した。
札幌農学校の教師たち
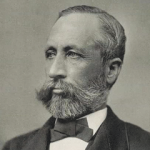
ウィリアム・S・クラーク
任期:1876.5~1877.5 担当:植物学、英語等
開拓使の求めによりマサチューセッツ農科大学長のまま、明治9年(1876)、6月に来日。8月開校の札幌農学校(現北海道大学)の初代教頭に就任。日本での滞在は僅か8ヶ月程度だったが、キリスト教精神に基づく人間教育等を行い、後に北海道の発展に貢献する人物を多数輩出した。

セシル・H・ピーボディ
任期:1878.12~1881.7 担当:数学、物理学、土木学等
土木工学と数学を担当した。新設の観象台(天文台)を管轄し,測量術・物理学・天文学・器械図法なども教えた。
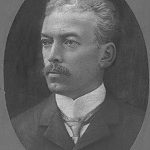
ウィリアム・ホイーラー
任期:1876.5~1879.12 担当:代数学、測量学、図学等
クラークの愛弟子で、共に来日。開拓使の土木顧問も担う。
渾名を「山羊」と呼ばれ学生間に人気があった。人格を認められ、農学校2代目の教頭を務めた。

ジェームス・サマーズ
任期:1880.6~1882.6 担当:英語
明治6年(1873)に来日し、東京開成学校や新潟、大阪の英学校でも教鞭をとった。
明治24年(1891)に日本で病死し横浜外人墓地に密葬。
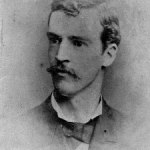
デビッド・P・ペンハロー
任期:1876.5~1880.8 担当:化学、植物学、英語等
クラークに同行。植物学を農学等の実学に応用するというクラークの考えを実践。
クラーク帰国後、教頭心得としてホイーラーを助ける。

ホーレス・E・ストックブリッジ
任期:1885.5~1889.1 担当:化学、農用化学、地質学等
明治18年来日。

ウィリアム・P・ブルックス
任期:1877.1~1888.10 担当:農学、植物学、農場実習等
明治10年(1877)1月来日。札幌農学校農学教師、校園長を担当した。玉蜀黍、甘藍(キャベツ)、亜麻、甜菜、玉ねぎなど北海道の特産的農作物を生み出した。さらに土地改良・馬耕を実地に指導し、農業経営の指導も行った。

ミルトン・ヘート(カナダ)
任期:1888.1~1892.8 担当:物理学
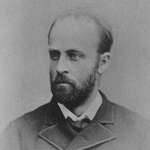
ジョン・C・カッター
任期:1878.9~1887.1 担当:数学、物理学、土木学等
札幌農学校の英語教育に貢献。契約外の歴史、経済、心理学等のリベラル・アーツ系の講義も務める。

アーサー・A・ブリガム
任期:1888.12~1893.11 担当:農学
明治21年(1888)来日。農学・植物学を担当し、農園長を兼務した。農業技術の普及のため、学外の農業団体にも指導を行った。